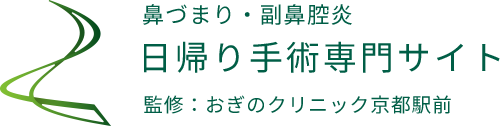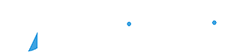- HOME>
- 薬剤性鼻炎
薬剤性鼻炎について

薬剤性鼻炎は、血管収縮薬を含む市販の鼻炎用スプレーを長期間にわたって日常的に使用することで引き起こされる鼻の疾患です。この状態では、鼻づまりの症状がかえって悪化し、薬剤への依存が生じる可能性があります。
薬剤性鼻炎の主な原因
- 血管収縮薬含有の市販鼻炎スプレーの長期使用
- 薬剤の効果減弱に伴う過剰使用
- 鼻粘膜の血管反応性の変化
など
薬剤性鼻炎の症状
主な症状には以下のようなものがあります。
- 持続的な鼻づまり
- 鼻炎スプレーの効果時間の短縮
- 鼻炎スプレー使用後の反動性鼻閉
- 鼻粘膜の腫脹や変色
- 嗅覚障害
など
薬剤性鼻炎を診断するために
詳細な問診
鼻炎スプレーの使用歴、頻度、期間などを確認します。
鼻腔内視鏡検査
鼻粘膜の状態、特に下鼻甲介の腫脹の程度を評価します。
鼻腔通気度検査
鼻づまりの程度を左右の鼻の鼻腔抵抗を測定することで客観的に評価します。
CT検査
必要に応じて、鼻腔や副鼻腔の詳細な状態を確認します。
薬剤性鼻炎を治療するには
原因薬剤の中止
最も重要な治療は、原因となっている血管収縮薬含有の鼻炎スプレーの使用を中止することです。ただし、中止するだけでは高度の鼻閉による睡眠障害等の懸念があるため代替治療を行いながら減量、中止を目指していきます。
代替療法
ステロイド点鼻薬
鼻粘膜の炎症を抑制し、長期的に症状の改善をはかります。血管収縮薬が含まれた点鼻薬とくらべて速効性はありませんが、根気よく継続し変更していくことが大切です。
生理食塩水による鼻洗浄(鼻うがい)
鼻腔内を清浄に保ち、粘膜の回復を促進します。当院ではまず0.9%の生理食塩水での鼻洗浄を勧めていますが、市販の点鼻薬からの離脱を目指して2.7%の高張食塩水スプレーの使用もお勧めしています。
経口抗ヒスタミン薬・抗ロイコトリエン受容体拮抗薬・抗ヒスタミン/血管収縮薬合剤
市販の点鼻薬の長期使用に伴う薬剤性鼻炎による鼻閉には、通常のアレルギー性鼻炎で処方される抗ヒスタミン薬の効果は限定的となります。その場合、抗ロイコトリエン受容体拮抗薬(モンテルカスト等)の追加を検討します。
また、重度な鼻閉に対しては一時的に抗ヒスタミン薬と血管収縮薬の合剤であるディレグラ®(フェキソフェナジン/プソイドエフェドリン合剤・プソフェキ)を処方することもあります。この薬剤は初回は14日までの処方制限があり、その後も1か月あたり30日までしか処方できません。また、高血圧、心臓疾患などへの影響を考え、高齢の方には処方しづらいこともあり、鼻うがいやステロイド点鼻薬を併用しながら最終的には減量を目指す薬となります。
手術療法
長期の薬剤使用により下鼻甲介が恒常的に腫脹し、代替治療によっても効果がみられない場合には手術治療を検討します。
粘膜下下鼻甲介骨切除術(内視鏡下鼻腔手術)
腫脹した下鼻甲介内で肥厚した骨を一部切除することで下鼻甲介のサイズを縮小し、空気の通り道を拡げます。
経鼻腔翼突管神経切除術(後鼻神経切断術)
過度な鼻汁産生、鼻粘膜の腫脹を引き起こす「指令」をしている鼻腔の後方にある翼突管神経後鼻枝(後鼻神経)を選択的に切断します。
薬剤性鼻炎の予防と注意点
- 市販の鼻炎スプレーは医師の指示がない限り、連続7日以上使用しない
- 症状が改善しない場合は自己判断で使用を継続せず、専門医を受診する
- アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などの基礎疾患がある場合は、適切な治療を受ける
- 生理食塩水による鼻洗浄を日常的に行い、鼻腔内を清潔に保つ
など
回復の過程と予後
薬剤性鼻炎からの回復には原因薬剤を中止して代替治療に切り替え、長期的に粘膜の状態が改善するのを待つ必要があります。手術治療の場合は手術後1~3か月で鼻内の状態が安定すると鼻閉が改善し市販の点鼻薬に頼ることはほぼなくなることが期待できます。
根本的な原因治療を行うことが重要
薬剤性鼻炎は、適切な治療と生活習慣の改善により克服可能な疾患です。市販の鼻炎スプレーに頼り続けるのではなく、根本的な原因治療を行うことが重要です。
当クリニックでは、患者様の状態を詳細に評価し、個々の状況に応じた最適な治療計画を提案いたします。鼻づまりでお悩みの方、特に市販の鼻炎スプレーを長期使用されている方は、一度専門医による診察をお受けください。
おぎのクリニック京都駅前の「鼻の治療」